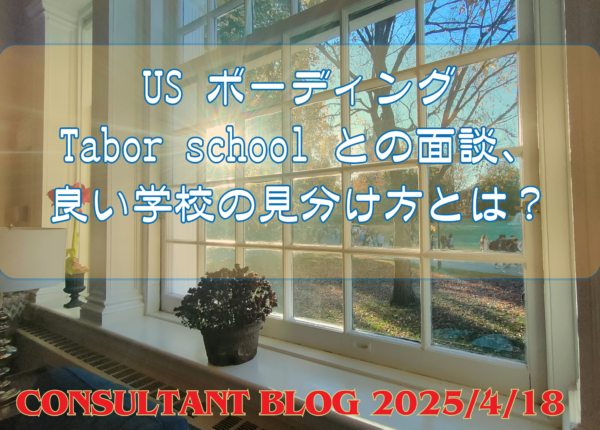留学物語-父は東大ぼくはニュージーランドその8 - 旅立ち
(その7 6月4日掲載)
ぼくの留学先はニュージーランド南島の人口2万人あまりの田舎の男子校に決まった。留学を決意してから渡航までが3ヶ月。日本の高校は退学した。日本にも、高校にも思い残すことなどなかった。ただ、高校を去って行ったぼくの友達のことは頭の片隅に残っていた。いつも気になっていた。できるなら友達と会いたかった。「会ってどうする」と大人は言いそうだが、ぼくはそれにうまく答えようとは思わない。
本当に自分が好きなことに理由などあるだろうか。あったとしても、それがうまく説明できる必要があるだろうか。
日本の高校での勉強はいつも正解が与えられた。ぼくがどう思うかでなく、あらかじめ用意された答えに最も早くたどり着く考え方を先生は教えた。「違う」と思った。ぼくの海外での生活はすくなくとも正解は用意などされていなかった。だから、ぼくは答えを探しまくった。それを高校の先生に言うと先生は沈黙した。
いつかぼくの友達と再会したら、こころはあの時代にすぐタイムスリップするだろう。いくつになっても、あの時のことは忘れない。そう思っていたい。白髪頭になっても、髪の毛が薄くなっても関係ない。つかの間でも生き生きとしている自分がぼくは好きだ。「現実はそれほど甘くはない」とぼくの先生は言った。そのままぼくはその言葉を先生に返した。現実が甘くないことは、先生よりもぼくのほうが海外で経験したと思う。先生の「現実」は、受験そのものだと思う。受験が終わったら現実は理想になるのだろうか。
成田空港に向かう車の中で、ぼくは日本での高校時代を振り返っていた。母は、車のなかで言葉は少なかったが、ぼくのニュージーランド行きが決まってから、とても陽気になっていた。父は働き盛りだから、日本とドバイを往復していた。スケジュールをやりくりして、ぼくを空港まで送ってくれている。ぼくの兄は父に似て勤勉で完璧を求めるような性癖がある。英語がとてもできた。4人が一緒というのは何ヶ月ぶりだろうか。
車のなかで静かに時間が過ぎ、いつもより早く成田空港に着いた。ぼくの精神は開放に向かっていた。もう納得できない勉強のプレッシャーにおびえる必要も戦う必要もない。でも、留学先での勉強はどうなるのだろうか。ニュージーランドにも日本と同じような勉強があったらどうなるのだろうか。サイトーさんは、「ニュージーランドには受験戦争はない」と言っていたが、本当だろうか。嘘をつく人ではないことはわかっているが、彼も大人だ、今までぼくは大人が言ったことをまともに信じられたことはない。サイトーさんと議論のないまま、この日を迎えた。